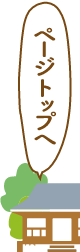園だより
2025.09.04
津市の現状について
先日、津市の教育長とお話する機会をいただきました。
その中で出た話は「津市の子どもたちの学力低下」について。
学習時間がかなり減っている現状があるとのこと。
その主な原因として考えられるのは…皆さんお察しの通り、ゲームやYouTube等(以下 ゲーム等)に夢中になり、学習に至らないことだそうです。
と聞くと、つい「最近の子どもたちはけしからん!」「ゲームやタブレット、スマホを取り上げよう!」という動きになってしまいそうですが…それはひとまず横に置いて、ここで少し一緒に考えてみたいと思います。
今、多くの子どもたちが常識的にゲーム等を所有しています。
誕生日やクリスマスのプレゼントとして、もしくはお年玉で。
ゲームを手に入れた我が子の喜ぶ姿は親として嬉しいものです。
また、学校のお友だちはみんな持っているのに我が子だけが持っていない状況を不憫に思い、親は我が子に対する 愛情の印として買い与えたりもします。
さらに、例えば就労その他の理由でお子さまと一緒に過ごせないとき、ゲーム等を与えていれば安心という考えもあるかと思います。
自分がそばにいてあげられないとき、ゲーム等で時間を過ごしてくれれば退屈や寂しい思いをすることもないだろうという親心。
しかし「親の心 子知らず」とはよく言ったもので「今日はお家の人がそばにいてくれるからゲームはしない」と子どもが自ら判断して止められるわけではないし、何より子どもは好奇心旺盛で楽しいことが大好き。
親の心とは反対にどこまででも、何時間でも没頭することでしょう。
それに対し「主体性」の名のもとに「自分のことは自分で決めればいい、あなたの人生だ」とつい任せ切りに。
結果として、宿題や学習に向かう時間、睡眠時間を惜しんでまで何時間もゲーム等に没頭し離れられなくなるという状態に陥っていくことになります。
ここまで考えてみて分かることは「子どもの学力低下」を子ども自身の責任とするのではなく「親の課題」として捉えていく必要もあるということです。
「ゲームし過ぎ」と注意をするとその都度言い合いや喧嘩になったりする。
親としてどうすれば良いのか分からない。
ならば、子どもの行動を変えるよりも先に、親が自分自身の行動を変える方が現実的で、課題にチャレンジし易いかも知れませんね。
いろいろな保護者さんとお話してみて、親ではゲーム等の魅力には勝てないと思っている方も結構いらっしゃるようです。
また、例えば公園のジャングルジムやブランコなんてつまらない、ゲーム等の方が面白い、子どもはそう思っていると勘違いされている大人の方も多いようです。
本当にそうでしょうか?
試しに、お子さまがゲーム等に没頭しているときにお散歩に誘ってみてください。
「外で一緒に遊ぼう!」「一緒にトランプしよう!」など…誘ってみてください。
お子さまはきっと嬉しそうな表情でゲーム機を置き、親のそばに来てくれるはずです。
子どもは「大好きな人と過ごす時間」を一番楽しくて安心で幸せだと感じるものだと思います。
それがゲームであれ、外遊びであれ。
「何で遊ぶか」よりも「誰と遊ぶか」です。
遊んでくれる人がいないから、話を聞いてくれる人がいないから、ゲーム等に夢中になるしかない。
つまり私が言い たいのは「お子さまと遊んでいますか?」ということです。
普段の遊び相手はゲーム等に任せて、 学習させたいときにだけ口を出したりしていませんか?
子どもは誰を信頼し、誰を好きになり、誰の言うことなら「聞いてもいい」と思うのか。
それは「遊んでくれる人」「関わってくれる人」「話を聞いてくれる人」です。
ですから一見まったく別問題に思われるかも知れませんが、子どもに学習をさせたいならば、まずは子どもと思いっきり遊び合える、関わり合える関係になる必要があるということです。
私たち大人が子どもたちにしてあげられることは、まずはここからだと思います。